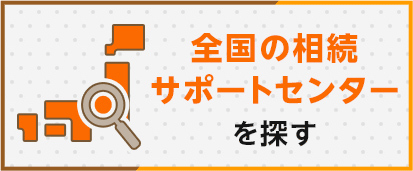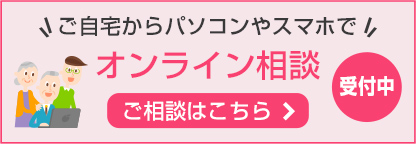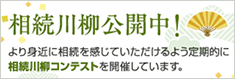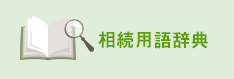「遺言書さえ書いておけば、相続は安心だ」 多くの方がそうお考えですが、実はそこに大きな落とし穴が潜んでいることがあります。それが、法律で定められた相続人の最低限の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」です。
今回は、この遺留分が原因で起こる典型的なトラブルと、それを未然に防ぐための最も有効な対策として「生命保険の活用」についてお話します。
そもそも「遺留分」とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)に法律上保障された、最低限の遺産の取り分のことです。
たとえ遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、他の相続人(例えば次男)は、自身の遺留分に相当する金額を、財産を多く受け取った長男に対して現金で支払うよう請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
よくあるトラブル事例:「実家を売るしかない…」長男の悲劇
ここで、典型的なトラブル事例をご紹介します。
- 状況: 被相続人(父)は、長年同居し家業も継いでくれた長男に感謝し、「全財産(評価額6,000万円の実家のみ)」を長男に相続させるという遺言書を遺しました。
- トラブルの発生: 遺言の内容を知った次男は、弁護士を通じて長男に自身の遺留分(6,000万円 × 1/4 = 1,500万円)を現金で支払うよう請求。
- 悲劇的な結末: 長男に1,500万円もの現預金はなく、やむを得ず、両親との思い出が詰まった実家を売却して支払うことに。兄弟の関係は完全に壊れてしまいました。
良かれと思って遺した遺言書が、かえって家族の絆を断ち切る引き金になってしまったのです。
なぜ生命保険が最強の対策になるのか?
この悲劇は、生命保険を活用していれば防ぐことができました。生命保険には、他の財産にはない3つの強力なメリットがあります。
1. 遺産分割の対象にならない「受取人固有の財産」である これが最大のポイントです。死亡保険金は、相続財産ではなく「保険金受取人の固有の財産」とみなされます。そのため、遺産分割協議で他の相続人と分ける必要がなく、指定された受取人が全額を確実に受け取れます。
2. 納税や遺留分支払いのための「現金」を準備できる 先の事例で、もし父親が「受取人:長男、死亡保険金:1,500万円」の生命保険に加入していれば、長男は受け取った保険金で、次男からの遺留分請求にスムーズに応じることができました。実家を売却する必要はなかったのです。
3. 相続税の「非課税枠」がある 死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」という大きな非課税枠があります。今回のケースでは、相続人が2人なので1,000万円まで非課税です。単に現金で1,500万円を遺すよりも、生命保険で遺した方が、相続税の負担を大きく軽減できるのです。
具体的な対策
不動産など、分けにくい財産を特定の相続人に渡したい場合は、 「その相続人を受取人として、他の相続人の遺留分相当額の死亡保険に加入しておく」 これが、円満相続を実現するための鉄則です。
相続対策は、ご家族の未来を守るための大切な準備です。 ご自身の状況で、どのくらいの備えが必要か、どのような保険が最適か、ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に当社までご相談ください。