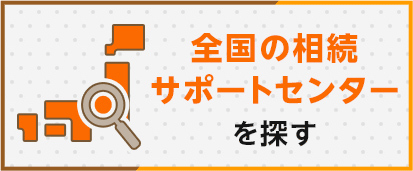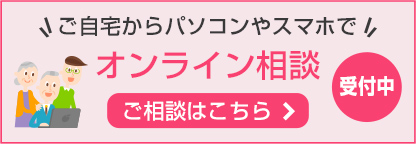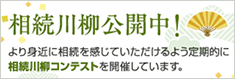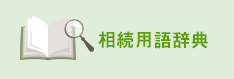はじめに
ある日、●●が亡くなったという連絡が入り、葬儀の手配に追われる中で、ふと「相続」の話が現実味を帯びてきます。「うちは財産なんてそんなにないから関係ない」と思っていた方も、実際に手続きが始まると、思った以上に煩雑で、相続税の対象になることもあります。
日本では、相続税が発生するケースは全体の1割程度といわれていますが、都市部に不動産を持っている家庭などでは、課税ラインを超えることも珍しくありません。相続は、感情的な問題と金銭的な問題が複雑に絡み合うため、事前の準備がとても重要です。
相続税の仕組みをざっくり解説
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する際にかかる税金です。
課税の有無は、「基礎控除額」を超えるかどうかで判断されます。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」となります。
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除は 4,800万円 になります。遺産の総額がこれを超えると、相続税が発生する可能性があります。
課税対象の財産には、預貯金や不動産、有価証券のほか、生命保険金や死亡退職金(非課税枠あり)、貸付金なども含まれます。一方で、借入金や未納税金などのマイナスの財産も差し引くことができます。
トラブルになりやすい「分け方」と「納税」
相続税が発生する場合、注意したいのが「誰がどの財産をどれだけ受け取るか」という分配の問題です。不動産のように分けにくい財産を巡って、親族間で意見が分かれるケースは多々あります。
また、相続税は相続した人がそれぞれ個別に納める仕組みのため、不動産を相続して現金を受け取っていない人にとっては、納税資金の確保が問題になります。
さらに、相続税の申告期限は「相続開始を知った日から10か月以内」と短いため、準備不足で慌ててしまうケースも見受けられます。土地の評価や相続人同士の調整など、時間がかかる工程が多いため、余裕をもった対策が必要です。
相続が始まったときの「分け方」と「節税」
配偶者が相続する財産が1億6,000万円までの場合は「配偶者税額軽減」という制度により支払う税額が 0 になります。
しかし、その先の二次相続まで考えた分け方をしないと一次、二次トータルの相続税が大きく変わることもありますので一次二次相続のシミュレーションが必要となります。
また、亡くなられた方が住んでいた自宅の土地については「小規模宅地等の特例」という制度により、一定の面積のうち80%の減額ができます。ですが、相続する方によって小規模宅地の特例が適用できない場合もありますので注意が必要です。
つまり、相続が始まった場合でも節税できる方法がありますが、特例を適用する場合は、分け方も重要となります。
円満な相続のために「今からできること」
まずは現状の財産の洗い出しを行うことが大切です。不動産や預金、有価証券などを一覧化しておくことで、相続人間の認識のズレを防げます。
また、専門家に早めに相談することで、「生命保険の加入」、「生前贈与」、「家族信託」や「遺言書の作成」など、税金対策や争族対策を講じることができます。特に、生前に不動産の共有名義を避けたり、納税資金を確保しておいたりすることは、後々のトラブル回避につながります。
おわりに
この記事では相続税の基本やトラブルを防ぐためにできることについて解説いたしました。相続は、誰にとっても避けて通れないテーマです。感情のもつれを防ぎ、大切な人との思い出を穏やかに受け継ぐためにも、できるだけ早い段階での準備がカギとなります。