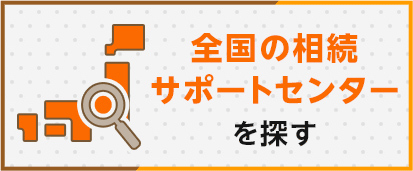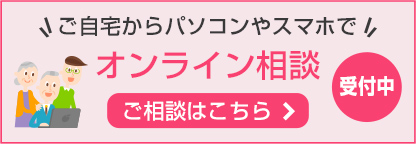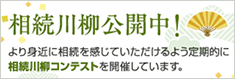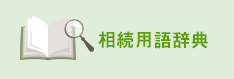はじめに
令和6年分の個人確定申告が終了しました。今年の確定申告では、110万円の贈与と併せて「相続時精算課税」の届け出をした人が多いのではないでしょうか?
110万円の非課税贈与は、相続税の節税対策として基本中の基本です。いかに効率的に110万円贈与を使いこなすかが、相続税節税対策の大前提となります。
そこで今回は、節税対策としての「110万円贈与」にテーマを絞り解説していきます。
1. 110万円贈与のメリットと生前贈与加算
相続税は、原則として被相続人が亡くなった時点での所有財産が課税対象となります。生前に相続人に対して贈与が成立している財産は、原則として課税対象外です。また、年間110万円までの贈与は、贈与税非課税です。
この制度を利用したのが「110万円の非課税贈与」です。例えば10年間子供二人に110万円ずつ贈与をすると2,200万円分(=110万円×10年×2人)の相続財産を減少させることができ、相続税の節税につながります。
しかし注意が必要なのは「生前贈与加算」です。相続税の計算上、「相続又は遺贈により遺産を取得した人(通常は法定相続人)に対する贈与について、死亡前7年分※の贈与は相続財産に持ち戻す。(前3年以内の贈与以外の贈与財産は、100万円までは加算しない)」というルールがあります。
【10年間子供二人に110万円ずつ贈与した場合の生前贈与加算額】
(110万円 × 7年〔持ち戻し期間〕- 100万円〔加算対象外〕)× 2人=1,340万円
つまり、死亡前10年間で総額2,200万円の贈与を実行したとしても、相続財産の減少額は、
860万円(=2,200万円-1,340万円〔生前贈与加算〕)のみという事になります。
※令和5年以前の贈与に関しては、持ち戻し期間は3年間。令和6年以降の贈与から持ち戻し期間7年となります。
2. 相続時精算課税の110万円非課税枠の活用
税務上の贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。上記で説明したのは、「暦年課税」の場合の取り扱いになります。
令和6年以降「相続時精算課税」に新たに「110万円の非課税枠」が創設されました。この非課税枠の最大の魅力は、生前贈与加算の対象外という事です。上述のケースで考えると、2,200万円(=110万円×10年×2名)全額を相続財産の減少としてとらえることが可能となります。
「110万円の非課税贈与」を考えた場合、圧倒的に「相続時精算課税」が有利といえます。
「相続時精算課税」は60歳以上の父母から、18歳以上の子や孫が贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署に届け出を出すことで選択できます。ただし、一度「相続時精算課税」を選択すると二度と「暦年課税」には戻れません。届け出の際は、税理士等と相談の上、慎重にご判断ください。
3. 贈与相手に応じて使い分け
結論としては、
子供に対する贈与=「相続時精算課税」
孫に対する贈与=「暦年課税」
となります。
孫は、基本的には法定相続人に該当しないため「生前贈与加算」の対象外です。通常の「暦年課税」で贈与していても、相続発生時に孫への贈与分を持ち戻すことはありません。
しかし、孫でも次の場合には子と同様に贈与財産が「生前贈与加算」の対象となります。
① 孫が代襲相続人として財産を取得する場合
② 孫が被相続人の養子として財産を取得する場合
③ 孫が遺言により財産を取得する場合
④ 孫が生命保険金の受取人となっている場合
このケースに該当する場合、「110万円の非課税贈与」を活用するためには、孫であっても「相続時精算課税」を選択する事を検討する価値は十分にあるといえます
4. 贈与実行時の注意点
生前贈与について「贈与は本当に実行されていたか?」という事が、税務調査の際にしばしば問題になります。(いわゆる「名義預金」問題です)
納税者:「相続人への贈与済みの財産は、相続財産に含めず相続税を計算しました。」
税務署:「贈与が実行されているとは認められません。相続財産に含めてください。」
この論点は、「贈与の事実」そのものを争っているため「暦年課税」「相続時精算課税」に関係なく生じます。「贈与の事実」が無かったと立証されると、時間をかけて実行してきた「110万円の非課税贈与」は無かったこととされ、不足分の相続税を収めることになります。
この事態を避けるためには、「贈与が実行」された証拠を残しておくことが重要です。ポイントは、「契約書の作成」「贈与の履行」「通帳等の管理」です。
① 契約書の作成
民法上贈与は「あげる」「もらう」というお互いの意思が確認できれば口頭でも成立します。契約書なしでも成立します。しかし、税務署に対して当事者間において贈与の意思があったことを証明するには「契約書の作成」が最も効果的です。来るべき相続税申告に備えて保管しておくことを推奨します。
② 贈与の履行(贈与財産の移転)
贈与財産(110万円)の移転は、贈与者から受贈者への銀行振り込みが望ましいです。現金で渡しても贈与は成立します。しかし税務署に対して贈与の事実を証明する意味では、通帳に記録を残しておいた方が確実といえます。
③ 通帳等の管理
税務上の贈与は「所有権の移転」の事実により認識します。ここでいう「所有権の移転」とは「管理・支配の移転」と読み替えることができます。
「親が子供名義の通帳に毎年110万円ずつ贈与して、通帳は親が管理していた。」というケースは、税務上「贈与の事実はなかった」こととされます。贈与を成立させるためには、通帳を子供に渡しておく必要がります。子供が110万円を本人の意思で自由に使える状況であるという事がポイントになります。
その他
① 未成年者(18歳未満)への贈与は可能?
結論としては未成年者への贈与は可能です。0歳児に対する贈与も可能です。
未成年者の場合、贈与契約や財産管理は親権者である親が代理で行うことになります。親権者が贈与契約書に署名押印のうえ、贈与財産を入金した通帳を管理していれば贈与は成立します。
しかし成人(満18歳)以降は、通帳を本人に渡しておかないと否認される可能性もあるのでご注意ください。
② 親が認知症になった場合
親が認知症の診断をうけた場合、以降の贈与は基本的に無効と考えられます。
贈与は、当事者の「あげる」「もらう」という意思確認が必要な法律行為です。認知症により意思能力が失われた状態では、法律行為を行うことはできなくなります。
ただし軽度の認知症であれば、医師の診断により意思能力があることが確認されれば「贈与実行」の可能性はあります。しかし確実に意思能力があったことの証明は困難なため、争った場合は最終的には裁判所の判断にゆだねざるを得ません。
5. まとめ
110万円の非課税贈与は、一見地味で時間もかかりますが、相続税の節税対策としては極めて効果的でかつ手続きも簡単です。しかし落とし穴もあるので、税理士等の専門家の意見を取り入れながら、確実に実行することをお勧めします。